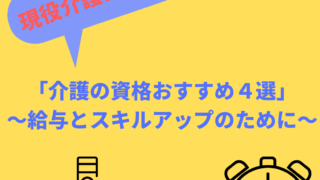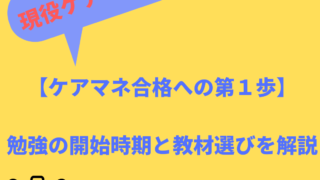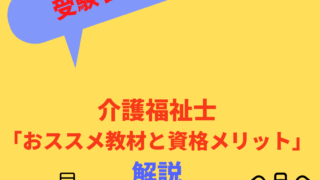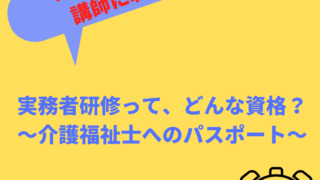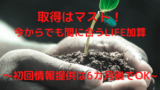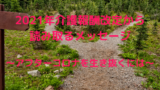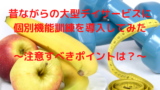「介護とPDCAサイクル」が改めて注目されています。
令和3年4月の介護報酬改定の目玉「LIFE」について詳細が分かってきました。
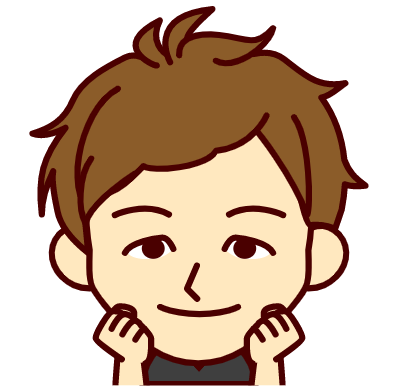
「LIFE」は、次のことを行い加算を得るシステムです。
①利用者の情報を国のデータベース「LIFE」に送る
②「LIFE」からのフィードバック(アドバイス)をケアに活かす
③その際に、「PDCAサイクル」を回す
④ケアの質を向上させる(自立支援と重度化防止の視点)
みなさん、こんにちは。
デイサービスで管理者をしている「ぽんてん」と申します。
今回の記事では、「介護のPDCAサイクル」について考えたいと思います。
介護とPDCAサイクルは、切っても切り離せない関係です。
しかも厚生労働省は、このように発表しています。
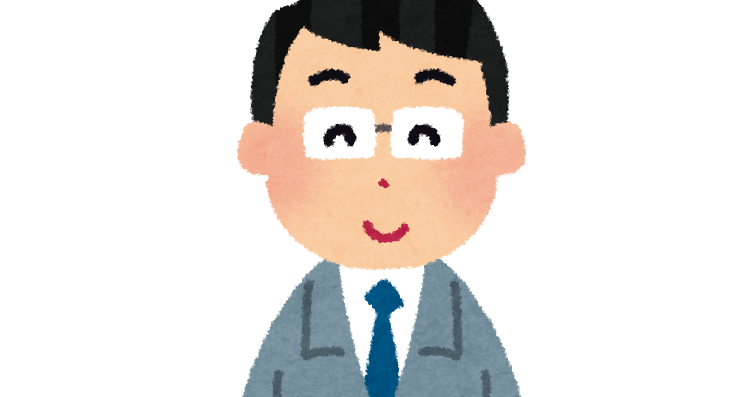
PDCAサイクルを行い、質の高いサービスを実施してくださいね。立ち止まらず常に改善を意識してください。情報をLIFEへ提供するだけでは加算はあげられまへんで~。
「PDCAサイクル」は重要です。
「PDCAサイクル」って何?という方にはもちろん、熟知している方にもご覧頂きたいと思います。
また、世の中には、
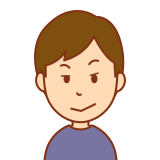
はあ?
今さら「PDCAサイクル」かよ!
だから介護は古くさいんだよ。
最先端は、「OODAループ」だぜ!
という意見もあります。
本当にPDCAサイクルが古いのかについても見ていきます。
それでは、今回のポイントです。
- PDCAサイクルのメリットは、継続的に品質管理や業務管理ができる点にある
- デメリットは、時間がかかること
- 介護で大切なのは、「チーム内の情報共有」
それでは、詳しく見ていきたいと思います!
PDCAサイクルとは

PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字を取ったもので、継続的に品質を管理するための手法です。
「品質」は介護に置き換えると、「利用者の健康やADL」と言えるでしょう。
厚生労働省は、次のように発表しています。
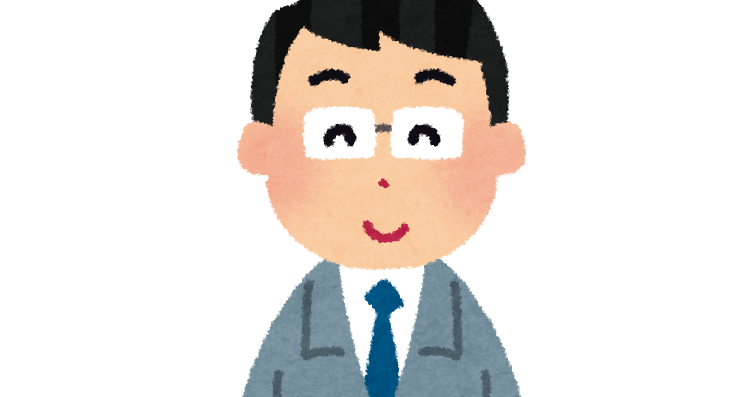
事業所は、利用者の自立支援・重度化防止を図る「サービス計画」を策定してください。提供しているサービスを多職種共同で検証し、「サービス計画」の見直しにつなげてくださいね~。
はい!出ました!
今年の超重要キーワード!
「自立支援と重度化防止」です!!
国には、もうお金がありません。
高齢者に元気でいてもらうことが、介護保険料を抑えることになります。
そのためにも、「PDCAサイクル」を理解する必要があります。
それでは、一つずつ見ていきましょう!
Plan(計画)
利用者の心身の状況などに関する基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための「サービス計画」を作成する
まずは、「こんな感じで利用者さんをケアしよう!」と計画を立てます。
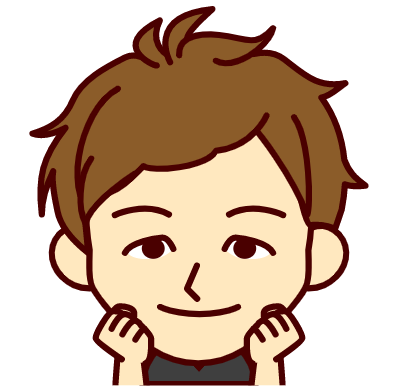
デイサービスでは、最初にケアマネさんから計画が来ます。
その計画に基づいて、デイサービスで計画を立てます。
施設であれば現場からケアマネジャーへ情報提供し、それから計画を立てることもあります。
Do(実行)
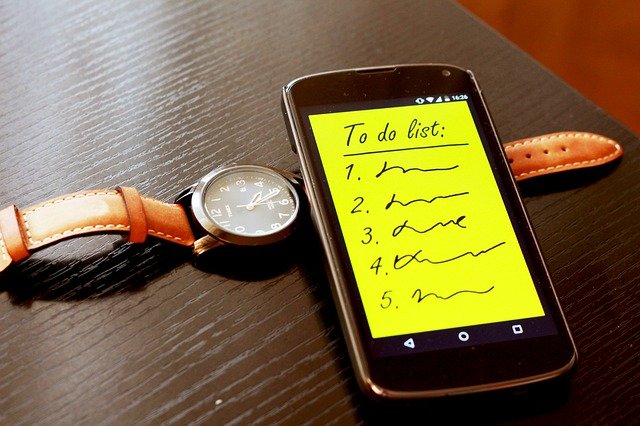
サービスの提供にあたっては、「サービス計画」に基づいて、利用者の自立支援・重度化防止に向けた介護を実施する
また出ましたね!
今年の超重要キーワードの「利用者の自立支援・重度化防止」が!
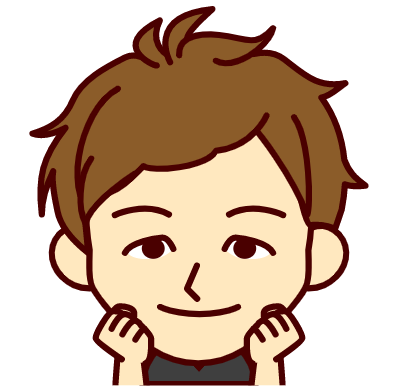
単にサービスを提供するだけではなく、「自立支援と重度化防止」を意識することが表記されています!
この辺りが、国の目指す方向なんですね!
Check(評価)
LIFEへ提出する情報、フィードバックの情報なども活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービスのあり方について検証を行う
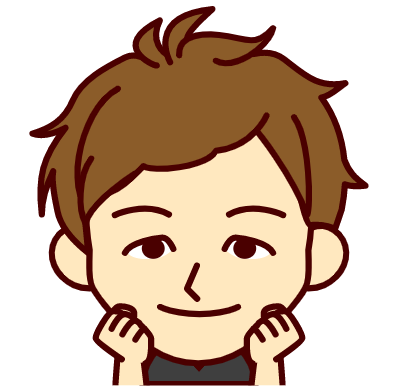
「事業所の特性について検証を行う」は面白いですね!
これからは、介護戦国時代の幕開け!
「生き残るために考えろ!」って感じですかね。
Action(改善)

検証結果に基づき、利用者の「サービス計画」を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める
「サービスの質の向上」とは、
国が求める「自立支援と重度化防止」に向けたサービスと言えるでしょう。
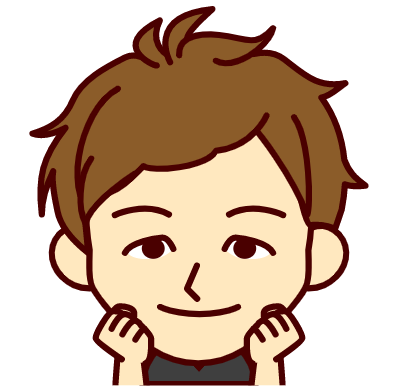
これまでのように、利用者さんから「ありがとう」を言ってもらいOK!ではなくなりそうですね!
筆者の事業所は「一日デイ」です。
お風呂や食事だけでなく、機能訓練なども必要になってきます。
ちなみに、筆者の事業所は「昔ながらのデイサービス」です。
今年2月から柔道整復師スタッフが加入してくれて、個別機能訓練を実施しています。
PDCAのメリットとデメリット
最大のメリットは、継続的に品質管理や業務改善ができること
計画を作成し、チームで実行。そして評価、改善。
ここでいう「品質管理」は、「利用者さんのADLや健康」です。
デメリットは、改善に時間がかかること
Plan、Do、Checkを行った後で、ようやくAction(改善)です。
どうしても、サイクルには時間がかかってしまうのがデメリットです。
介護で大切なことは?

もっとも大切なのは、「チーム内の情報共有」が出来ていることでしょう。
PDCAが形式になってしまうと、もう最悪です。機能しません。
例えば、現場の様子がケアマネジャーに正しく伝わっているか?
ということです。
「情報の共有化」が出来ていなければ、改善は望めません。
OODAとは?

直接LIFEとは関係ありませんが、「OODAループ」という考え方をご紹介します。
なぜかと申しますと、「OODAループ」は「PDCAサイクル」のライバルと呼ばれているからです。
例えるなら、甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信。
ドラゴンクエストとファイナルファンタジー。
シャ乱Qとウルフルズ。
巨人と・・・もういいですね。
Observe(観察)、Orient(状況判断、方針決定)、Decide(意思決定)、Act(行動)の頭文字を取ったもので、問題解決のメソッドの1つ。スピード感がウリ。しかし、個人で考え行動することが前提であり、チームの統制が難しいとされる。
PlanとDoがない分、スピード感ある対応が可能です。
「様子を見て・・・。よし!やってみよう!」
みたいな感じですね。
もともとは、航空戦を行うパイロットに向けて開発されたといわれています。
個人の判断が必要な緊急の場面では優れています。
介護やPDCAが「時代おくれ説」は本当か

ときどきSNSなどで、
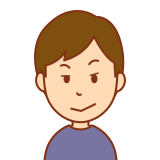
今どき、「PDCAサイクル」って・・・(笑)
だから、介護は時代遅れなんだよ!
みたいな意見があります。
それぞれ、自身の解釈があって当然です。
しかし筆者は、
PDCAは介護に適していると思います。
利用者の健康やADLを維持するためには、多職種の観察や意見が必要だからです。
色んな角度から総合的に判断して、
「こうやったらどうかな?」
「次は、この方法でやってみよう!」
と、チームで歩んでいくのが介護だからです。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、LIFE加算でますます重要になる「PDCAサイクル」について見てきました。
「PDCAサイクル」自体は、すでに介護業界で行われています。
重要なのは政府が、
「サービスの提供にあたり、利用者の自立支援・重度化防止に向けた介護を実施する」
ことを明記している点です。
これまでのような、「お風呂に入ってご飯食べてOK!」の時代は終わりです。
自身の特性を打ち出せない事業所は、淘汰されるでしょう。
それでは、今回のおさらいです。
- PDCAサイクルのメリットは、継続的に品質管理や業務管理ができる点にある
- デメリットは、時間がかかること
- 介護で大切なのは、ケアマネジャーと現場との連携
Plan:利用者の心身の状況などに関する基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための「サービス計画」を作成する
Do : 利用者の心身の状況などに関する基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための「サービス計画」を作成する
Check : LIFEへ提出する情報、フィードバックの情報なども活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービスのあり方について検証を行う
Action : 検証結果に基づき、利用者の「サービス計画」を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める
ライバルの「OODA」は次の通りです。
Observe(観察)、Orient(状況判断、方針決定)、Decide(意思決定)、Act(行動)の頭文字を取ったもので、問題解決のメソッドの1つ。スピード感がウリ。しかし、個人で考え行動することが必要であり、チームの統制が難しいとされる。
どちらが新しい古いではなく、
介護にはPDCAサイクルが適しています。
多職種で様々な角度から利用者を観察することが必要だからです。
「自立支援と重度化防止」が実現すれば、政府も利用者もハッピーです。
利用者さんがハッピーなら、私たちもハッピーです。
時代の流れに乗り、利用者・スタッフ・事業所を守っていきたいですね。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。