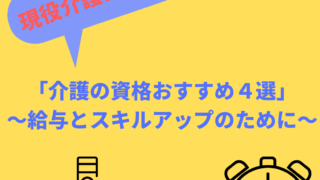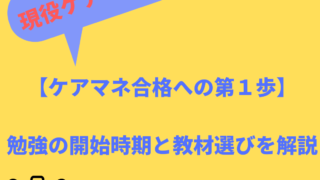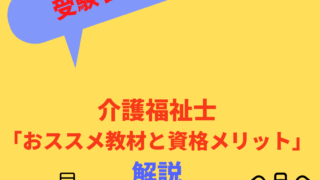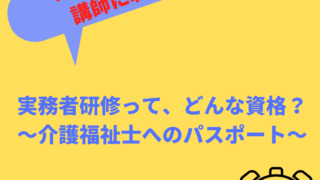皆さん、こんにちは。
初心者ケアマネの「ぽんてん」です。
今回は、「認知症の歴史」についてお話したいと思います。
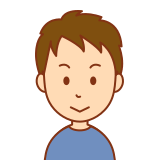
認知症って、いつからあったのかな?
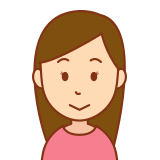
昔は、何て呼ばれてたのかなあ?
どんなふうにケアされてたんだろう・・・
ふと、こんな風に考えたことはありませんか?
今回は、「認知症の歴史」に関する内容です。
難しい内容は、一切出てきません。
サラっと読める内容ですので、
介護職の方も、そうでない方も是非お付き合いください。
それでは、今回のポイントです。
- 古代にも認知症はあった(紫式部の記述にも残る)
- 江戸時代の事例が多く残されている
- 温かいケア、身体拘束や虐待に通じるケアがあった
- 名称の経緯は、「老狂、物狂い」→「痴呆」→「認知症」
- 「認知症」の名称は、国民投票で決まった?
- 海外に比べてもスゴイ!!日本の「配慮力」
それでは、詳しく見ていきたいと思います!
認知症は、いつからあった?

まずはじめに、認知症はいつからあったのでしょう?
認知症の記述は、古代にまで遡ります。
なんと、紫式部が記述に残しているのです!!
紫式部と言えば、源氏物語ですよね!
「源氏物語」を完成させたのが1010年くらいと言われます。(諸説あり)
ですから、少なくとも平安時代には「認知症の人」は居たことになります!
ちなみに紫式部は認知症の人を、
「惚け痴る」(ほけしる)
と表現しています。
※「惚(ほ)ける」=「ボーっとする」の意味
現代の「惚れる」につながっているのでしょうね。
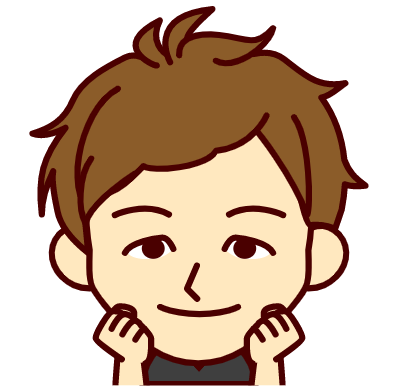
あの紫式部も、認知症の人を表現していたとは!
さっそく明日、話のネタに使えますね(笑)
そういえば高校生の頃、「古語辞典」使ってたなあ…。
次章では、江戸時代の認知症について紹介します!
バラエティー豊か!「江戸時代の認知症」

さて、時代は進みます。
江戸時代の「認知症」についてです。
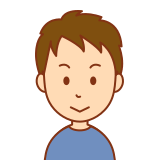
そもそも江戸時代に高齢者って、どれくらいいたの?
ある資料では、人口の約10%は80歳以上だったらしいです。
意外に多いと感じました。
江戸時代ともなると、かなり詳しい記述が残っています。
江戸時代の事例
江戸時代の記録には、バラエティーに富む事例が残されています。
その中から、3つ取り上げます。
- 昼夜、ウロウロと歩き回る(いわゆる徘徊)
- 子供のように玩具で遊ぶ
- 急に夜中に驚く(せん妄)
いかがでしょう?
現代の認知症と同じ症状ですよね。
「認知症は、時代に関わらず存在した」と言えます。
次章では、江戸時代の「認知症ケア」について見ていきます。
江戸時代の「認知症ケア」

日本人の道徳観がつくられたのは、江戸時代といわれています。
そうです!「儒教の精神」です。
「君主に忠誠を誓い、親孝行をする」
こういった考え方ですね。
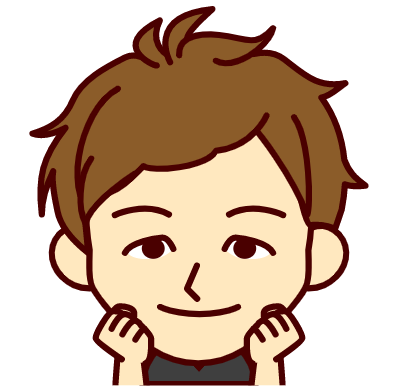
親孝行をすることは藩からも奨励されていました。
手厚い介護を行い、ご褒美をもらうこともあったようです。
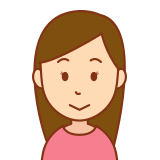
親の介護をして褒美をもらうなんて・・・
現代では考えられないわ・・・
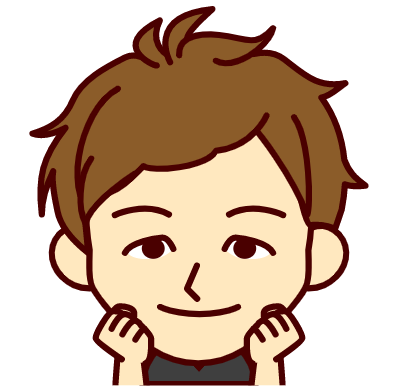
そうですよね。
中には、認知症の母を抱きながら寝る若夫婦の事例もあります。
そうすると、落ち着いて寝られたんだとか。
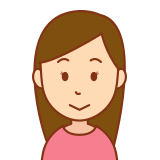
それって、今の認知症ケアに通じるものもありますね!
やっぱり、大事なのは「人の温かさ」なんだ!
江戸時代って、スゴイ!

お褒めの言葉、ありがたきこと・・・。
私は、江戸時代の医師でございます・・・。
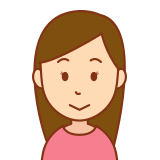
いきなりですね・・・。

江戸の介護は、良いものばかりではありませぬ。
「術(すべ)無し」として、中には紐で縛り付けたり、部屋に閉じ込めることもありました・・・。
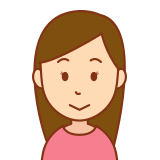
そうだったんですね・・・。
現代でも、身体拘束を行うことはあります。
家族の同意が必要ですけど・・・。

そうでしたか・・・。令和の時代でも、特効薬はないようですなあ。
ちなみに江戸時代でも「身体拘束」を行う際は、家人などが署名をし奉行所などへ届け出る決まりがあったのですじゃ・・・。
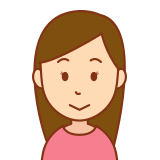
ええ~~!
今と一緒です!!

驚かれたようじゃな・・・。
正当な理由なしに、認知症の親に食事を与えず切腹を申し付けられた人もいるのじゃよ・・・。
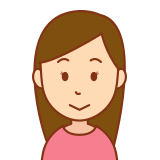
切腹!
今より厳しかったんですね・・・。
いきなり江戸時代の医師と、現代の介護スタッフの会話をご覧いただきました(笑)
こうやってみると、江戸時代と現代に共通することが多いのも興味深いですね。
次章は、認知症の名称についてです。
認知症の名称

この章では、認知症の名称についてお話しします。
古代、平安時代から記述が残っています。
実は古代から大正時代くらいまでは、決まった呼び方はありませんでした。
「ほけひと」「物狂い」「老狂」
このような呼び方をされていました。
時は流れて1960年代(昭和)、ようやく「痴呆症」という言葉が定着します。
大正時代から使用されていたとも言われています。
そして時は流れて2004年、
ついに「認知症」という名称に決定されました。
次章は、「認知症」という名称が決定する経緯についてです。
認知症は、「名前の総選挙」で選ばれた?

昭和中期から、ずっと「痴呆症」という呼び名が使用されていました。
しかし、この痴呆症には重大な問題が…。
それは、痴呆という漢字にあります。
「痴」=「あろかな、狂う」
「呆」=「ぼんやり、魂の抜けた」
かなり厳しい言葉ですよね。
認知症の人の尊厳を無視していると考えられたのです。
そして、いよいよ国が動きます!

「痴呆」に代わる用語に関する検討会をつくります!
候補を挙げるので、国民投票で国民の意見を聞きたい!
そして、国民に投票を呼びかけ「認知症」に決定したのです!
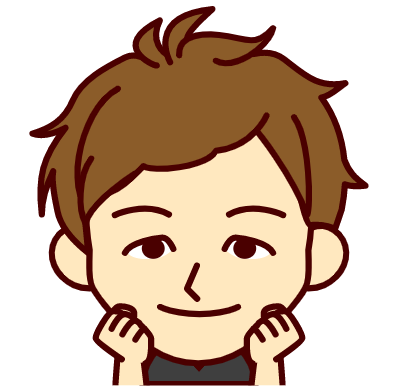
投票第1位は、「認知障害」だったようです。
しかし、「認知症」の方が柔らかい表現であり採用されました。
今も、厚労省のホームページから見ることが出来ます。
次章は、海外諸国との比較です!
ニッポンの「配慮力」はすごい!
それでは、海外では「認知症」をなんと呼ぶのでしょう?
英語・・・ dementia
韓国・・・ 痴呆
中国・・・ 失智
いかがでしょうか?
英語は、「精神から乖離する」というような意味らしいです。
韓国は、以前の日本と同じ。
中国も、いかにもといった言葉ですね。
いかに日本が「配慮」に長けているか分かります。
まとめ

いかがでしょうか?
今回は、認知症の歴史について見てきました。
古代(平安時代)にも記述が残されていたり、江戸時代にも身体拘束があったり・・・。
筆者としては、
「不安がる親を放っておけず、夫婦で抱き合って寝る」
という温かいケアに感動しました。
認知症に対して知識も薬もない中、懸命にケアしていたことに敬意を表します。
それでは、今回のおさらいです。
- 古代にも認知症はあった(紫式部の記述にも残る)
- 江戸時代の事例が多く残されている
- 温かいケア、身体拘束や虐待に通じるケアがあった
- 名称の経緯は、「老狂、物狂い」→「痴呆」→「認知症」
- 「認知症」の名称は、国民投票で決まった?
- 海外に比べてもスゴイ!!日本の「配慮力」
今回あらためて、「認知症」って歴史が長いようで短い不思議な病気だと感じました。
皆さんは、どのように感じましたか?
是非コメントお願いいたします!