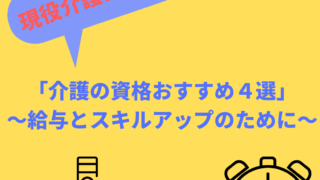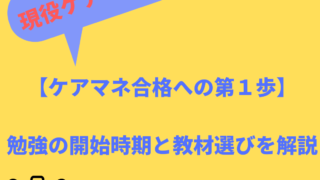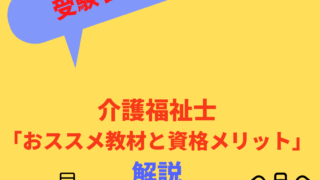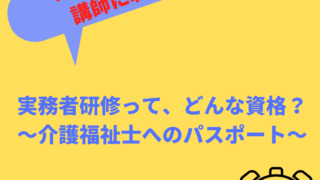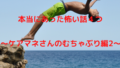はじめに
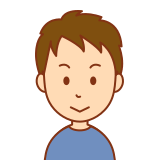
介護施設に勤務しています。転倒事故が起こって裁判になるケースがあると聞いて不安です。
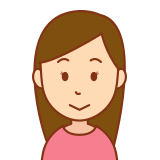
一生懸命仕事をしていても、防げない事故もあるし・・・。
食事介助も、万一誤嚥したらと思うと怖くって・・・。
こんな風に不安に思っている人も居られると思います。
令和2年8月27日の社会保障会議で、介護保険施設の経営者で組織する団体の代表がある問題を提起しました。
要約すると・・・、
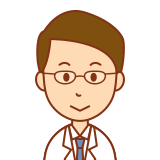
転倒や誤嚥は事故ではなく、高齢化による自然な現象だ。裁判にまで発展し、敗訴になることも多い。国の見方を変えてくれ!
という内容です。
私は、デイサービスで管理者をしています。
介護に携わる一人として、この問題について考えてみたいと思います。
今回の記事は、介護事故について真剣に考えてみたいと思っている人に向けて書かれています。
この記事を読むと、次のことが分かります。
- 介護事故が、裁判にまで発展してしまう多くの理由
- 事故の際、施設に最も必要なのは・・・
結論は、以下の通りです。
- 事故が起きた後、施設側が謝罪や説明を十分に行わず家族の信頼を損なうケースが多い
- 最も大切なのは、施設側の「誠意」
それでは、詳しく見て行きたいと思います。
記事の作成のため、次の書籍を参考にさせて頂きました。
「裁判例から学ぶ介護事故対応」外岡 潤〔著〕 第一法規より
転倒や誤嚥は事故なのか?
介護経営者代表の問題提起とは

令和2年8月27日の社会保障会議で、介護保険施設の経営者で組織する団体の代表が問題提起しました。
「転倒や転落、誤嚥を事故と認定することについて少し意見を言いたい。例えば、認知症で危険の意識がなく歩行能力も衰えている方などが転倒されるということは、もう事故ではなく老年症候群の1つの症状ではないかと思う」
「転倒や転落、誤嚥は本当に事故なのか、ということも検討して頂きたい」(原文のまま)
簡単にまとめると、
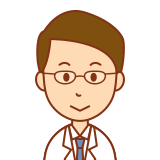
転倒や誤嚥は事故ではなく、老化現象の一つだ。裁判にまで発展させないで欲しい。
という内容です。
一生懸命ケアしていても、転倒や誤嚥は起こるものだという考え方です。
なぜ裁判にまで発展してしまうのか

転倒や誤嚥といった事故が起きると、裁判にまで発展することがあります。
家族側にしても、施設にお世話になっているという気持ちはあるはずです。
それでは、なぜ裁判になってしまうのでしょうか?
多くの場合は、「相互不信」が原因と言われています。
「お互いが信じられない」状態です。
今回は、転倒事故について考えていきたいと思います。
転倒事故が裁判に発展する理由

転倒事故が裁判にまで発展してしまう多くの理由に、
- 施設側から十分な説明や謝罪が無く、利用者側の不信感が増大してしまう
- 報告が遅れ、利用者の容体が悪化。利用者側の怒りを買ってしまう
この2つが挙げられます。
家族側には、施設に「お世話になっている」という気持ちがあるはずです。

施設からの報告が、遅いし不十分だ。誠意を持って謝罪してくれたら、裁判にまでするつもりは無かったのに・・・。
このように思いながらも、施設への不信感が募り裁判へ発展するケースが多いのです。
つまり、家族の信頼を得れば、裁判は回避できます。
深刻な事態を回避するために、
- 家族への事故報告は、迅速に行う。(事実を伝える)
- 今後の対応方針について、同意を得る
- 誠意を持って謝罪する
家族への報告について
家人へ報告する際は、事実のみを伝えましょう。
転倒であれば、その瞬間を見ていなければ「私が発見した時には、床に尻もちをついておられた」など、事実のみを伝えるのです。
今後の方針について、同意を得る
そして、これからの対応方針を伝えて利用者側の同意を得ておくことです。
同意を得ることで、後のトラブルを防ぎます。
「施設に放っておかれた」や「施設が勝手に○○した」などと言われなくなります。
誠意を持って謝罪する
謝罪は誠意を持って行いますが、必要以上に施設を卑下しないことです。
「施設でこのようなことになり、申し訳ございません。」
のように、一言添えるだけで、ほとんどの家族の気持ちは収まります。
まとめ

今回は、「施設内での転倒が裁判にまで発展してしまう理由」について見てきました。
家族側には、「施設にお世話になっている」気持ちがあるのに裁判を起こしてしまう。
その理由は2つです。
- 施設側から十分な説明や謝罪が無く、利用者側の不信感が増大してしまう
- 報告が遅れ、利用者の容体が悪化。利用者側の怒りを買ってしまう
それは、
ご利用者側の信頼を得れば、裁判にまで発展するリスクを低く抑えられる
ことを意味します。
ご家族の信頼を得るためには、
- 家族への事故報告は、迅速に行う。(事実を伝える)
- 今後の対応方針について、同意を得る
- 誠意を持って謝罪する
この3つを行うことです。
「事故の瞬間」を見ていなければ、「床に尻もちを突いていた」や「トイレで座り込んでいた」など事実をありのままに伝えましょう。
次に、病院受診の有無など「今後の方針」について同意を得ます。
謝罪を行う際には、必要以上に自分や施設を卑下しません。
しかし、心を込めて行いましょう。
「施設で、このようなことになり、申し訳ございません」など、一言添えるだけで大きく相手の印象は変わります。
大切なのは、「誠意」です。
「信頼関係」は、裁判に発展してしまうリスクを最小にします。
事故について、ご家族側は何も見えません。
一つ一つ、誤解のないように伝えることが一番大切です。
日頃の努力が報われるためにも、リスク管理は大切です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。