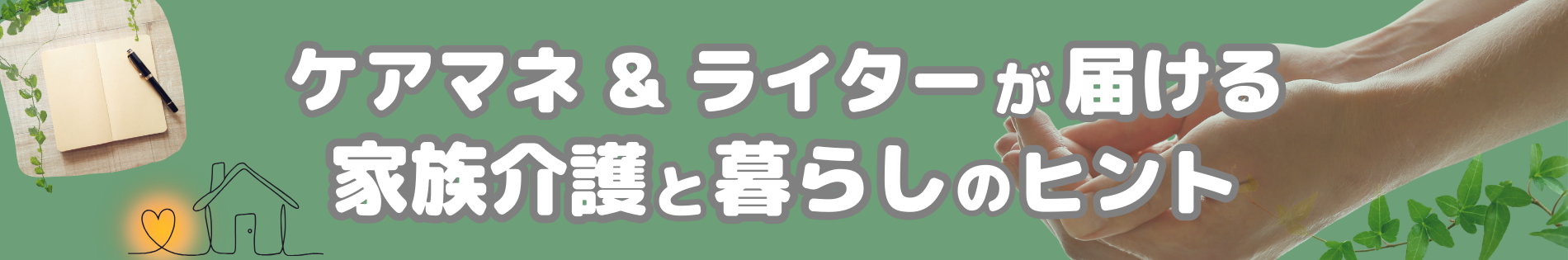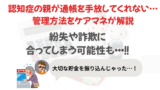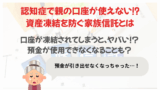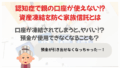「成年後見制度って難しそう…」「家族信託と何が違うの?」
そう感じていませんか?
ご本人の認知症が進むと、お金の管理や生活の判断を、ご家族が代わりに行う必要が出てきます。そのときの選択肢が「成年後見制度」と「家族信託」です。
どちらも、ご本人やご家族の権利・財産を守る制度ですが、タイミングや目的によって適する制度は異なります。
この記事では、現役ケアマネジャーの視点から、以下のことを分かりやすく解説します。
- 成年後見制度のしくみ
- 家族信託との違い
- わが家に合った選び方のヒント
「どちらが正解?」ではなく「ご本人・ご家族に必要な仕組みを知っておく」ことが大切です。資産管理について後悔しないために、ぜひ最後までお読みください。
成年後見制度とは?

認知症や障がいなどで、判断力が低下してしまった方をサポートする法律が「成年後見制度」です。ご本人の権利や財産を守るために、家庭裁判所が「後見人」を選び、本人の代わりに必要な手続きや管理を行います。
制度の基本と目的
成年後見制度の目的は「判断力が低下した方を法的にサポートし、ご本人の生活を守ること」です。
具体的には、以下のようなサポートがあります。
- ご本人名義の銀行口座からの出金や振込
- 不動産の売却や賃貸契約
- 福祉サービスの契約や入院手続き
以上のような「法的に有効な契約行為」を、ご本人が行えなくなったとき、代わりに対応するのが後見人の役割です。
【参考】厚生労働省「成年後見人等の選任と役割」
※認知症とお金のトラブルについて、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
ご本人の代わりにできること・できないこと
成年後見制度で「できること・できないこと」の例は、以下のとおりです。
◯できること
- お金の出し入れなどの手続き
- 税金や保険料の支払い
- 医療・介護サービスの手続き
- 不動産の売却や財産の管理(家庭裁判所の許可が必要)
◯できないこと
- ご本人の意思に反する医療行為(手術の同意など)
- 買い物や家事(宅配サービスや生活支援などの契約は可能)
- 後見人自身の利益になる契約(利益相反行為)
成年後見制度は、あくまで「ご本人の利益を守る」ための制度です。よって、ご本人の意思を尊重し、慎重に判断・行動する必要があります。
【参考】厚生労働省「成年後見人などは何をしてくれるの?」「成年後見人などにお願いできないことは?」
後見人の種類は2つ(法定後見・任意後見)
成年後見制度には、大きく分けて2種類があります。
| 種類 | 開始のタイミング | 誰が決める? | 特徴 |
| 法定後見 | 判断能力が低下した「あと」 | 家庭裁判所が選任 | 実際の状況に応じた支援内容になります |
| 任意後見 | 判断能力がある「うちに」契約 | 本人が選んだ人と契約 | 将来に備えて準備できますが、発効には家庭裁判所の判断が必要です |
今すぐ支援が必要な場合は「法定後見」、将来に備えるなら「任意後見」というイメージです。
【参考】法務省「成年後見制度について」
家族信託と成年後見制度の違いとは?

「家族信託」と「成年後見制度」は、どちらも判断力が不安になったときのための制度です。しかし、目的や使い方、柔軟性には大きな違いがあります。ここでは、制度ごとの特性を分かりやすく比較していきましょう。
開始時期の違い(元気なうち or 判断力低下後)
一番大きな違いは「いつから使える制度なのか?」という点です。
- 家族信託:ご本人が元気で、契約内容を理解できるうちに
- 成年後見制度:ご本人の判断力が低下してから
つまり、家族信託は「元気なうちの備え」、成年後見制度は「すでに困っているときの対処法」という役割の違いがあります。
※家族信託について、さらに知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
柔軟性・費用・手続きの違い
「家族信託」と「成年後見制度」の違いを、以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
| 柔軟性 | ご家族など信頼できる方が対応するため、柔軟性は高いです。 | 家庭裁判所の監督下で管理するため、柔軟性は低いです。 |
| 管理対象 | 契約で定めた財産に限定されます。 | すべての財産を管理します。 |
| 専門家費用 | 初期費用は数十万円かかることもありますが、信託開始後の運用コストは月額数千円程度に抑えられる場合が多いです。 | 裁判所申立てや後見人報酬が必要。月額費用が数万円必要であり、高コストになる傾向にあります。 |
| 裁判所の関与 | なし | あり(定期報告・監督) |
家族信託は「設計次第で、柔軟に対応できる」というメリットがあります。また、成年後見制度は家庭裁判所を経由するため、ケースによっては「やや柔軟性に欠ける」と感じる場面もあるかもしれません。
家族信託と成年後見制度、どちらがご家族に合っている?
迷ったときの判断材料として、それぞれの制度に向いているケースを分かりやすく整理しました。ぜひ参考にしてください。
◯家族信託が向いている人
- ご本人が元気で、将来について話し合える
- 相続対策や資産の活用も視野に入れておきたい
- 財産を柔軟に管理・活用したい
- 通帳や不動産など、管理を任せたい財産がはっきりしている
- 家庭裁判所の関与なく、家族の中で運用したい
◯成年後見制度が向いている人
- すでにご本人の認知症が進行し、判断力の低下がみられる
- 金銭トラブルや詐欺のリスクが高まっている
- 親族間に不信感があり、第三者の関与が必要と感じている
- 裁判所の監督のもと、法的にしっかり管理したい
それぞれの制度には特徴があり、使いどころが異なります。ご家庭の状況や、将来の見通しに合わせて、どちらがフィットするかを慎重に検討していきましょう。
制度選びに迷ったときのポイント

家族信託と成年後見制度には、それぞれにメリットがあり、どちらが正解というわけではありません。大切なのは「ご本人の状態」と「ご家族の希望」に合わせて、最適な制度を選ぶことです。
「ご本人が元気」なら信託が有力
ご本人に判断力があるうちに話し合えるなら、家族信託が選択肢になります。不動産や預金の管理方法を話し合いながら、契約内容を自由に設計できるため、相続や資産活用も想定した準備が可能です。
「いざというときに慌てたくない」「家族の中で柔軟に管理したい」というご家族にとって、家族信託は心強い制度といえるでしょう。
「認知症が進行している状態」なら後見制度へ
もし、すでにご本人の認知症が進んでいる場合には、家族信託の利用は難しくなります。この場合、ご本人の権利を法的に守る成年後見制度を検討しましょう。
裁判所が関与することで、第三者の目が入り、トラブルを未然に防ぎやすくなります。判断力の低下が明らかなときは、速やかに申立ての準備を進めることが大切です。
併用や切り替えはできるの?
基本的に、家族信託と成年後見制度は併用することも可能です。たとえば、家族信託で管理しきれない部分を後見制度で補うといった形で、補完的に活用されるケースもあります。
また、信託契約を結んでいたけれど、後見人による管理が必要になったときには、後見制度への移行・併用が検討されることもあります。制度は「どちらかを選ぶ」ではなく「組み合わせて使う」ことも視野に入れておきましょう。
成年後見制度の申し込み手続きと費用

成年後見制度は、家庭裁判所を通じて申立てを行い、選ばれた後見人が本人の代わりに財産管理などを行う仕組みです。ここでは、実際に利用する際の手続きの流れや費用の目安について分かりやすく解説します。
家庭裁判所での手続きの流れ
具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。
- 申立ての準備
必要な書類(申立書、診断書、財産目録など)をそろえます。診断書は、本人の判断能力を医師が評価したものが必要です。
- 家庭裁判所に申し立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立てができるのは、配偶者や親族、または市区町村長などです。
- 家庭裁判所による調査・審理
家庭裁判所が本人の状況を確認し、必要に応じて面接や鑑定が行われます。
- 後見人の選任と審判
審理を経て、適切な後見人が選ばれ、審判によって制度の利用が開始されます。
※手続きには通常、1〜2カ月程度かかりますが、ケースによっては数カ月かかることもあります。
かかる費用の目安(申立費用・報酬など)
- 申立て時の実費:数千円〜1万円程度(収入印紙・郵便切手・医師の診断書料など)
- 鑑定費用(必要な場合):5万円〜10万円程度
- 後見人の報酬:家庭裁判所の判断で月額2万円〜5万円程度が相場
※報酬は、ご本人の資産や管理内容に応じて増減します。費用面は、あらかじめどれくらいの負担になるかを想定しておくと安心です。
専門家に依頼する場合の注意点
申し立てや手続きが不安な場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談・依頼することも可能です。
ただし、依頼料として10万円〜20万円前後の費用がかかることが多いため、家計や本人の資産状況に応じて検討しましょう。「どこまで自分たちでできるか」「専門家のサポートが必要か」などを整理したうえで、無理のない形で進めるのがポイントです。
まとめ:大切なのは「いつ」制度を活用するか
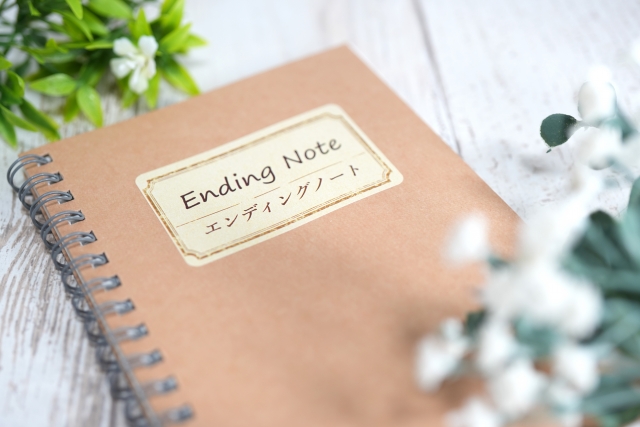
成年後見制度と家族信託は、どちらも「家族の財産と安心な暮らしを守るための制度」です。ただし、特徴や活用するタイミングはまったく異なります。
「まだ先のこと」と思っていても、突然必要になるのが介護です。私は介護現場で、そんなケースに何度も立ち会ってきました。
だからこそ大切なのは「今、できるうちに」「もしもに備えて」準備しておくことです。
制度の違いを知り、ご家族の状況に合った選択ができれば、さまざまなトラブルを避けられる可能性は高くなります。