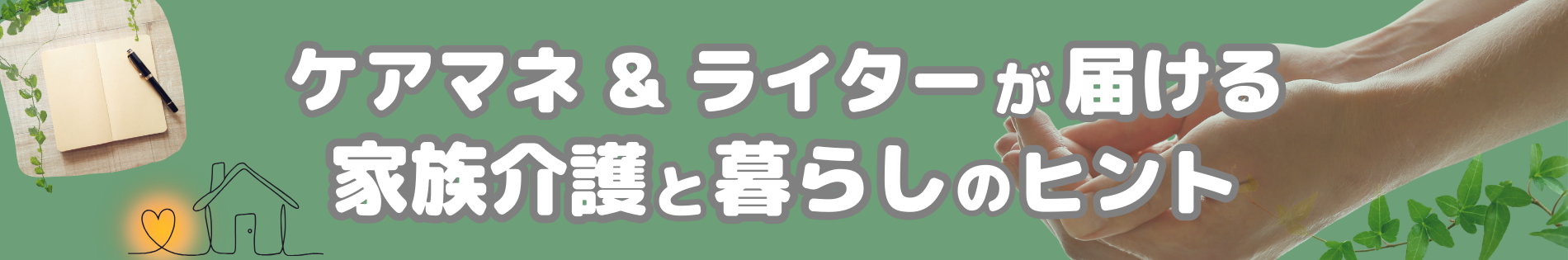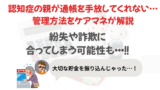「親の介護、お金がなくてどうしよう…」「費用が払えないかもしれない。誰に相談すれば…」
このような不安やお悩みはありませんか?どうか、ひとりで抱え込まないでください。
介護の経済的な負担は、公的な制度を正しく利用すれば、大きく軽減できます。お金がなくても、介護で悩む必要はありません。

現役ケアマネジャーとして、多くの相談に乗ってきました。この記事では、介護費用に困ったときの具体的な対処法から相談窓口までをわかりやすく解説します。
- まずは、現状の把握が大切
- 在宅介護と施設介護の費用
- 介護費用の負担を減らす7つの制度
- 世帯分離や生活保護についての基礎知識
- 今からできる「介護とお金」の備え
この記事を読むと、ご本人とご家族に合った選択肢が必ず見つかりますので、ぜひ最後までお読みください。
親の介護にお金がない…でも大丈夫!最初に行うべき3つのステップ
ご家族の介護でお金がないと気づいた時、多くの方が不安を感じます。しかし、正しい手順を踏めば、必ず解決できます。必要なのは、以下の3つです。
- 現状を把握する
- ひとりで抱え込まず専門家に相談する
- 利用できる公的制度の存在を知る
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ステップ1:現状を正確に把握する
まず「お金の流れ」を把握しましょう。何に、いくらかかっているのかを書き出して「見える化」することが大切です。具体的に「いくら不足している」と理解できれば、対策を立てやすくなります。
例えば、介護サービス費や医療費、食費などの支出と、年金収入や預貯金といった収入・資産を書き出してみましょう。
ステップ2:ひとりで抱え込まず専門家に相談する
介護やお金の問題を、ひとりで抱え込まないことが重要です。担当ケアマネジャーや、お住まいの市区町村にある「地域包括支援センター」へ相談しましょう。

相談は無料です。誰かに話を聞いてもらうだけでも、精神的な負担が軽くなり、客観的に状況を見つめ直すきっかけにもなります。
ステップ3:利用できる公的制度の存在を知る
日本には、介護の経済的負担を軽減するための公的制度が数多くあります。介護費用を補助する制度や、税金の負担が軽くなる仕組みなどさまざまです。
例えば、1ヶ月の自己負担額に上限を設けて、それを超えた分が払い戻される「高額介護サービス費制度」などが代表的です。
これらの制度を利用するには申請が必要な場合が多いため、まずはどのような制度があるかを知ることから始めましょう。
【費用一覧】親の介護にかかるお金|在宅介護 vs 施設介護

ここでは、在宅介護と施設介護、それぞれの「初期費用」と「月額費用」の目安について解説します。それでは、一緒にみていきましょう。
在宅介護の費用目安(初期費用+月額)
在宅介護の場合、初期費用として平均74万円、月々の費用として平均4.8万円ほどかかるといわれています。ご自宅で安全に暮らすためには、手すりの設置や段差の解消といった住宅改修が必要になることがあり、これが初期費用の主な内訳です。
もちろん、住宅改修が不要な場合は初期費用を大きく抑えられます。月々の費用は、デイサービスや訪問介護といった介護保険サービスの自己負担額が中心となります。
その他、おむつ代や医療費なども考慮しておく必要があるでしょう。

ここでご紹介している費用は、あくまでも平均です。ご本人の介護度状態によって、必要な介護費用は大きく異なります。
施設介護の費用目安(初期費用+月額)
施設介護で必要となる費用は、初期費用・月額費用共に施設によって大きな差があるのが特徴です。
特に、初期費用である「入居一時金」は0円から数千万円と非常に幅広くなっています。例えば、公的な施設である特別養護老人ホームでは、原則として入居一時金はかかりません。
一方、民間の有料老人ホームでは、入居一時金が0円の施設から、数千万円に及ぶ施設まで様々です。
また、入居してからの月額費用は平均12.2万円となっていますが、施設の種別や居室のタイプ、サービスの充実度で料金は大きく変わります。
【参考】生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(P.174)

最近は、インフレの影響もあり、食費などが値上げされている傾向にあります。以前よりも、入居者さんやご家族の負担は大きくなってきているのが現状です。
※施設入所の際に、費用を抑える方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。
知っておきたい!介護費用の負担を減らす7つの制度

ここでは、介護費用の負担を軽減するための制度を7つ紹介します。
①高額介護サービス費制度|払い過ぎた自己負担額が戻ってくる
高額介護サービス費制度は、介護サービスの自己負担額が上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。所得に応じて月々の自己負担上限額が定められており、それを超えた金額が後日支給されます。
制度を利用するには、市区町村の窓口での申請が必要です。
【参考】厚生労働省「高額介護サービス費制度が見直されます」
②負担限度額認定|施設の食費・居住費が安くなる
負担限度額認定は、介護保険施設にショートステイや入所されている方の食費や居住費(滞在費)の負担を軽減する制度です。介護保険施設を利用する際の食費や居住費は自己負担となるため、所得が低い方にとっては大きな負担となることがあります。
この制度を利用すると、所得や資産の状況に応じて食費や居住費の上限額が設定され、それ以上の金額は支払う必要がなくなります。申請には「介護保険負担限度額認定証」が必要ですので、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
【参考】厚生労働省「介護保険施設等における居住費の負担限度額認定」
③高額医療・高額介護合算療養費制度|医療費も介護費も高額な世帯へ
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費と介護費の両方が高額になった世帯の負担を軽減するための制度です。病気や怪我で医療機関にかかる費用と、介護サービスを利用する費用が重なると、家計への負担は大きくなります。
この制度は、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療費と介護費の自己負担額を合算し、世帯の所得に応じた上限額を超えた分が払い戻される仕組みです。
【参考】厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」

医療費と介護費の両方で困っている場合は、この制度の対象となる可能性がありますので、ぜひ確認してみてください。
④社会福祉法人等による利用者負担軽減制度|さらに負担を軽減
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度は、所得の低い方や生活保護を受けている方などを対象に、介護サービスの自己負担額や食費・居住費をさらに軽減する制度です。
介護保険制度には、さまざまな負担軽減策があります。それでもなお、経済的に厳しい状況にある方のために、社会福祉法人などが提供するサービスの費用負担を軽減するものです。
この制度を利用できるかどうかは、お住まいの市区町村や利用する社会福祉法人によって異なりますので、まずは相談窓口で確認してみましょう。
【参考】横浜市「社会福祉法人による利用者負担軽減について」
⑤生活福祉資金貸付制度|一時的にお金を借りる
生活福祉資金貸付制度は、一時的に生活が困窮している世帯に対して、生活を立て直すために必要な資金を貸し付ける制度です。介護費用が急に必要になったものの、手元に十分な資金がないといった場合に、この制度を利用してお金を借りられます。
例えば、介護に必要な住宅改修費や、介護サービス利用料の一時的な立て替えなどに活用することが可能です。貸付には審査があり、返済の義務も伴います。お住まいの市区町村の社会福祉協議会が窓口です。
【参考】政府広報オンライン「生活にお困りで一時的に資金が必要なかたへ 生活福祉資金貸付制度」があります」
⑥医療費控除|確定申告で税金が戻る
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽減される制度です。介護サービスの中には、医療費控除の対象となるものも含まれており、例えば訪問看護や介護老人保健施設などの利用料の一部が該当します。
確定申告を行い、支払った税金の一部が戻ってくる可能性がありますので、介護費用だけでなく医療費もかかっている場合は、ぜひ活用したい制度です。領収書をしっかりと保管し、忘れずに確定申告を行いましょう。
【参考】国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
⑦自治体独自の助成制度|お住まいの市区町村を必ずチェック
自治体独自の助成制度は、国が定める介護保険制度とは別に、各市区町村が独自に設けている介護に関する支援制度です。国の制度だけではカバーしきれない部分や、地域の実情に応じたきめ細やかな支援を提供するために設けられています。
例えば、おむつ代の助成や、介護用品の購入費補助、見守りサービスの提供など、その内容はさまざまです。

お住まいの地域によって利用できる制度が異なりますので、まずは市区町村の介護保険課や地域包括支援センターに問い合わせて、どのような制度があるかを確認しましょう。
親の介護でお金がない場合にできること|施設入所と世帯分離

ここでは、公的施設への入所や世帯分離について解説します。
費用を抑えられる公的施設への入所を検討する
介護費用を抑えたい場合、公的施設への入居を検討しましょう。公的施設は、民間施設に比べて利用料が安く設定されているため、経済的な負担を大きく軽減できる可能性があります。
特に「特別養護老人ホーム(特養)」は、入居一時金が不要で、月額費用も比較的安価な点が特徴です。ただし、特養は入居希望者が多く、待機期間が長くなる傾向があります。そのため、早めに情報収集を始め、複数の施設に問い合わせて入居条件や空き状況を確認し、申請手続きを進めることが大切です。
ただし、最近では、特養と同程度の月額費用で入所できる有料老人ホームも増えてきています。すぐに施設入所を希望される方は、検討されることをおすすめします。
「世帯分離」のメリット・デメリット
介護費用を軽減する一つの方法として、「世帯分離」があります。これは、同じ住所に住みながらも住民票上は別の世帯として登録する手続きです。
世帯分離を行うと、介護保険サービスの自己負担割合や高額介護サービス費の上限額が、ご本人の所得のみで計算されるようになり、結果として介護費用が安くなる可能性があります。
しかし、世帯分離にはデメリットもあります。例えば、国民健康保険料が世帯ごとに発生し、世帯全体の保険料が増える可能性や、扶養控除が受けられなくなるなどの影響です。そのため、世帯分離を検討する際は、メリットとデメリットを理解し、事前に市区町村の窓口や専門家に相談することが重要です。
【参考】調布市「世帯変更届:世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき」
どうしても親の介護費用が払えない…最終手段としての「生活保護」

さまざまな制度を活用しても介護費用の捻出が難しい場合、最後のセーフティーネットとして生活保護制度があります。
- 生活保護制度とは?介護費用はどうなる?
- 親が生活保護を受けるための条件と手続き
- 生活保護を受けながら介護施設に入ることはできる?
それぞれ一緒にみていきましょう。

「生活保護制度」は、国民に保障された正当な権利です。ためらわずに情報を得ることからはじめましょう。
生活保護制度とは?介護費用はどうなる?
生活保護は、ご本人の能力・資産などをすべて活用しても生活に困窮する方に対し、国が最低限度の生活を保障する制度です。介護が必要な場合、介護費用は「介護扶助」という仕組みから支払われるため、自己負担は原則ありません。
介護保険の自己負担1割分が介護扶助から給付されるため、負担なく介護サービスを利用できます。費用は事業者へ直接支払われるため、ご家族が現金を管理する必要もありません。
【参考】厚生労働省「生活保護制度について」
ご本人が生活保護を受けるための条件と手続き
ご本人が生活保護を受けるには、預貯金や不動産といった資産、年金などの収入、ご親族からの援助などをすべて活用しても、世帯全体の収入が国の定める最低生活費に満たないことが条件です。
手続きは、お住まいの地域を管轄する福祉事務所の窓口です。申請後、ケースワーカーによる家庭訪問や資産調査、ご親族への扶養能力の照会などが行われ、受給の可否が決定されます。
生活保護を受けながら介護施設に入ることはできる?
生活保護を受けながら、介護施設に入居することは可能です。施設の費用は、家賃相当分が「住宅扶助」、食費や日用品費が「生活扶助」、介護サービス費が「介護扶助」から、それぞれの基準額の範囲内で支払われます。
ただし、入居できるのは、特別養護老人ホームなどの公的施設が中心です。民間施設でも受け入れ可能な場合がありますが、扶助の範囲内で収まる施設に限られるため、選択肢は限られるのが実情です。担当のケースワーカーやケアマネジャーと相談しながら方向性を決定していきましょう。
【参考】横浜市「介護扶助について」
慌てないために!今からできる「介護とお金」の備え

お金のことで慌てないためには、事前準備が大切です。2つの点について、親子で話し合っておくとよいでしょう。
- ご本人の資産状況を共有しておく
- 介護の希望を話し合っておく
それぞれ詳しく解説します。
ご本人の資産状況(年金・貯蓄・保険)を親子で共有しておく
まず、ご本人の資産状況を、親子間で共有しておきましょう。介護が必要になった際、どのような選択肢がとれるのかを検討するためには、お金に関する正確な情報が不可欠だからです。
例えば、年金収入や預貯金の額、加入している生命保険などを把握できていれば、利用できる介護サービスや施設の予算を立てやすくなります。特に、認知症などで判断能力が低下すると、預金口座が凍結されてしまうリスクもあるため、元気なうちからの情報共有が重要です。
お金に関する認知症の方への対応については、こちらの記事で詳しく解説しています。
介護が必要になったらどうしたいか、希望を話し合っておく
お金の問題と併せて、ご本人が「どのような介護を望んでいるのか」を話し合っておきましょう。ご本人の希望を知っておくと、いざというときに迷わず方針を決められます。
「住み慣れた自宅で過ごしたい」「施設に入居したい」など、具体的な希望を聞いておくことが大切です。元気なうちにこそ、お互いの想いを伝え合っておきましょう。
知っていると得する!介護に使えるお金の知識

上記以外にも、特定の状況で経済的負担を軽くできる支援制度があります。ここでは、特に知っておくと役立つ2つの知識をご紹介します。
- 遠距離介護の交通費を節約する割引制度
- 自宅のバリアフリー化に使えるリフォーム補助金
ご自身の状況に合わせて、活用を検討してみてください。
遠距離介護の交通費を節約する割引制度
遠方にお住まいのご家族を介護している場合は、交通費の負担を軽減できる割引制度の活用を検討してみましょう。航空会社などが介護のための割引運賃を設けています。
例えば、J航空会社の「介護帰省割引」などです。これらの制度を利用するには、要介護認定を受けていることや、三親等以内の親族であることなど、各社が定める条件を満たす必要があります。
事前に申請や登録が必要な場合がほとんどなので、利用する交通機関のホームページなどで詳細を確認しておきましょう。
【参考】日本航空株式会社「ディスカウントご利用案内」
自宅のバリアフリー化に使えるリフォーム補助金
在宅介護を選択する場合、ご自宅のバリアフリー化などに必要な費用の一部を補助する制度があります。手すりの設置や段差の解消といった住宅改修が対象です。
介護保険の「住宅改修費の支給」制度で、要介護認定を受けている方を対象に、上限20万円までの工事費用のうち7〜9割が支給されます。

お住まいの自治体が独自に補助金制度を設けている場合もありますので、改修を検討する際は、まず担当のケアマネジャーや市区町村の窓口に相談してみましょう。
まとめ:親の介護でお金に困ったら、悩まず専門家へ

今回は、介護費用がなく困った場合の対処法や、負担を軽減する公的制度について解説しました。
一番お伝えしたいのは、問題をひとりで抱え込まず、できるだけ早く専門家へ相談することです。介護には、さまざまな公的支援が用意されており、専門家は状況に合わせた最適な解決策を一緒に考えてくれます。
担当のケアマネジャーや、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」で、お気軽に連絡してみてください。

相談に行く際は、ステップ1でまとめた「お金の流れ」がわかるもの(年金収入額、支出の内訳など)を持参すると、話がスムーズに進みます。「何に困っていて、どうなりたいのか」を具体的に伝えられるよう、簡単にメモしておくだけでも大丈夫です。
この記事が、介護のお金に関する不安を少しでも和らげ、最適な選択ができるきっかけになれば幸いです。