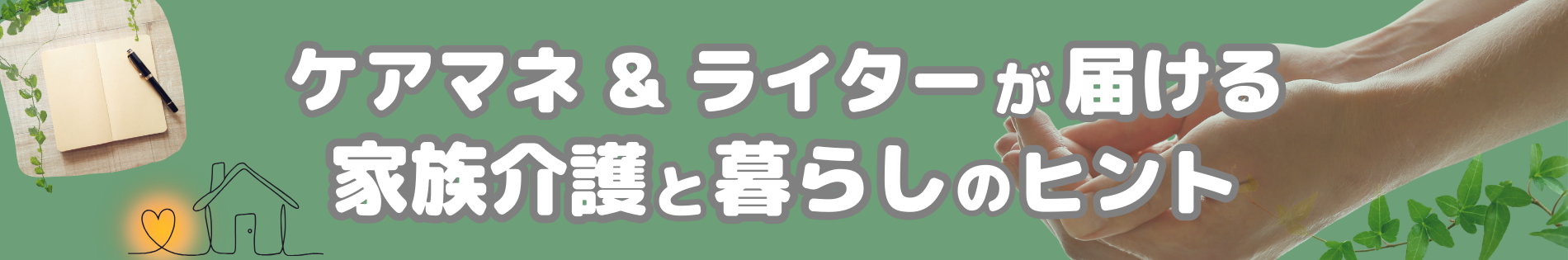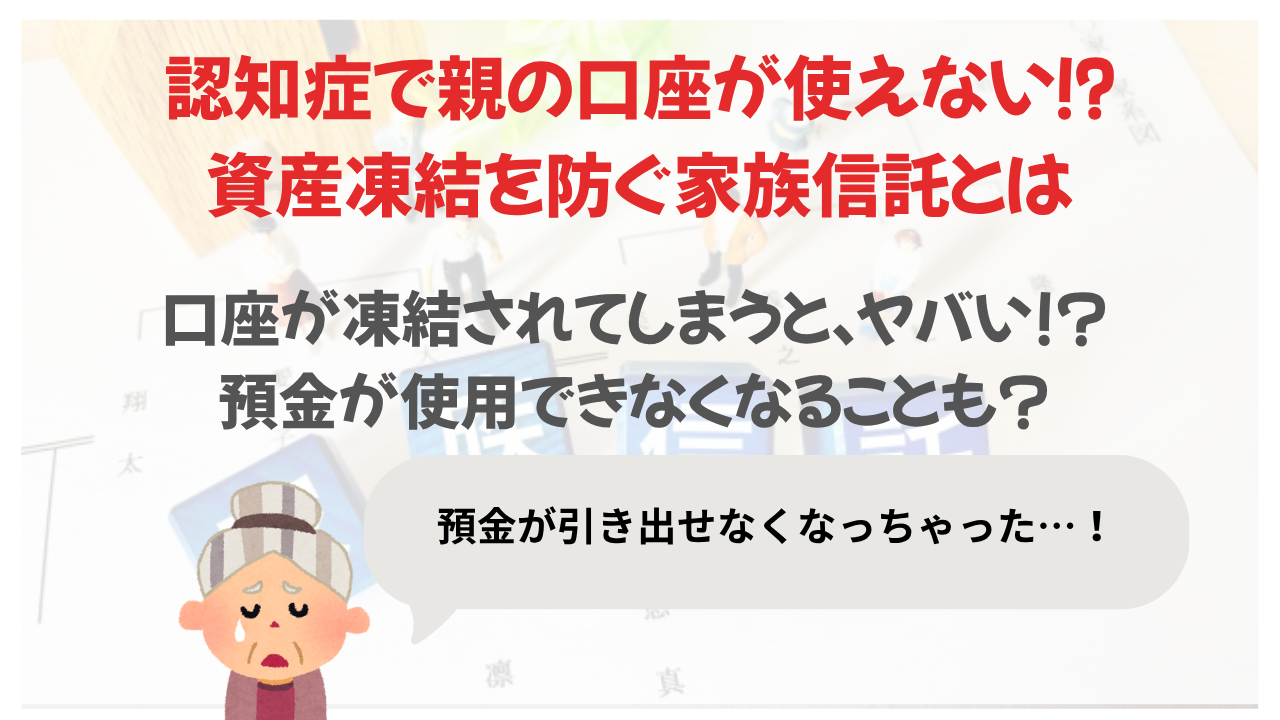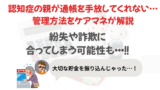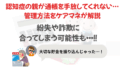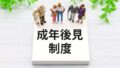「親の口座が凍結されたら…生活費や介護費はどうなるの?」「家族信託ってよく聞くけど、どんな仕組みなのか分からない」
そんな不安や疑問を感じていませんか?
認知症が進行すると、ご本人名義の口座が凍結されてしまい、お金が引き出せなくなるリスクがあります。生活費や施設費の支払いに困るのはもちろん、ご家族の間でトラブルになってしまうことも少なくありません。

銀行口座が凍結されて、預金が引き出せなくなることがあるんですか?

そうですね。私は、現役ケアマネジャーとして多くの方と接していますが、実際に預金が引き出せなくなて大変だったというお話を聞いたことがあります。
今回は、資産凍結を防ぐための方法について解説していきます。
「家族信託について、詳しく聞きたい」と考えている方は、家族信託の契約数NO.1の「おやとこ」の無料相談をご活用ください。
司法書士などの家族信託の専門家が、お客様のご状況に合わせた家族信託の無料相談を行っています。全国に7拠点を構え、年間数千件もの家族信託の問い合わせに対応しています。
認知症で口座が凍結されるとどうなる?困ること3選

銀行などの金融機関では、ご本人の判断力が低下していると分かった時点で、口座の出し入れを一時的に止める対応がとられることがあります。これは「詐欺などから守るため」という目的もありますが、ご家族にとっても深刻な問題になることがあるのです。
ここでは、認知症による資産凍結で起こりやすい困りごとを3つに絞ってご紹介します。
① 介護費・生活費が引き出せず支払いが滞る
ご本人の口座から引き落とせなくなると、介護施設の利用料などの支払いが滞ってしまうことがあります。
また、光熱費や家賃なども、ご家族が立て替えたり緊急対応に追われたりすることもあるかもしれません。
② 相続とは違う「生前の管理」の問題が出てくる
資産凍結と聞くと「相続の話かな?」と思われるかもしれません。しかし、これはご本人が「生きている間」の話です。
ご本人が元気なうちは自由に管理できていたお金が、認知症の進行と共に「使えなくなるリスク」として現れるのが、資産凍結の怖さです。
③ 複数人で共有管理できず、ご家族の負担が偏る
通帳やキャッシュカードを、ご本人が管理していた場合、ご家族は口座にアクセスできなくなる可能性があります。
「お兄さんが実家にいて通帳を持っているけど、妹さんは何も分からない」「親のことを一人で見ているのに、兄弟間で協力が得られない」など、ご家族内で役割と情報のバランスが取れていない状況が起きることがあります。

資産凍結は「ある日突然起きる」というよりも、徐々に起きていた問題が表面化するタイミングといえるでしょう。だからこそ「元気だから大丈夫」ではなく、「もしものとき」に備えておくことが大切です。
家族信託とは?認知症による資産凍結を防ぐ仕組み

最近、資産凍結への備えとして注目が高まっているのが「家族信託(かぞくしんたく)」です。言葉を聞くと、難しそうに感じるかもしれませんが、仕組みはシンプルです。
まずは、3人の登場人物を押さえよう(委託者・受託者・受益者)
家族信託とは「将来に備えて、お金や不動産の管理を信頼できる家族に任せておく契約」です。
登場人物は、以下の3人です。
たとえば、親が子に対して「認知症などで、将来お金の管理が難しくなったら、代わりにお願いね」と信託契約を結ぶことで、子が法的に通帳や不動産を管理できるようになるのが特徴です。
成年後見制度との違い
家族信託とよく比較されるのが「成年後見制度」です。
| 利用開始時期 | 本人が元気なうち | 判断能力が低下したあと |
| 柔軟性 | 高い(設計次第) | 公的なルールに沿う必要あり |
| 手続き | 契約で完結(登記あり) | 裁判所を通す必要あり |
| 管理範囲 | 柔軟に選べる(不動産・金銭など) | 全体的に包括管理するケースが多い |
本人の判断力がしっかりしているうちに準備するなら「家族信託」、すでに判断力が低下している場合は「成年後見制度」が検討対象になります。
なぜ「元気なうち」が大切なのか?
家族信託は、あくまでも「契約」によって成立する制度です。そのため、ご本人に「契約の意味を理解するための判断力」が求められます。
つまり「認知症が進行してからでは遅い」のがポイントです。「まだ大丈夫」と先送りにすると、必要になったときに利用できないリスクもあります。
だからこそ「今は元気だけど、これからが心配」という段階が、家族信託の準備を始めるべきタイミングなのです。
ご家族が通帳を手放してくれないなど、お金のトラブルへの対応方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
家族信託のメリット・デメリットをわかりやすく解説

家族信託はとても便利な制度ですが、メリットばかりではありません。導入を考えるときにはメリットと注意点の両方を理解しておくことが大切です。
ここでは、現場でよく相談されるポイントをもとに、家族信託のメリット・デメリットを整理していきます。
メリットは柔軟性・資産凍結の予防・相続対策にも有効なこと
メリットとして、以下の3つが挙げられます。
- ご本人の判断力があるうちに自由に設計できる → 信託財産の範囲や管理方法、いつ誰に何を引き継ぐかなど、ご家族の状況に合わせて設計できます。
- 口座凍結を防ぎ、介護費や生活費の支払いがスムーズに → 将来的に判断力が落ちた場合でも、信託契約に基づいてご家族が資産を管理できます。
- 相続対策としても応用可能 → 遺言と違い「生きているうちから財産の流れをコントロールできる」のが信託の強みです。
デメリットは費用・設計の複雑さ・制度理解の難しさ
注意点は、以下の3つです。
- 契約内容の設計が難しく、専門家の力が必要 → 曖昧な設計だとトラブルの原因に。司法書士や弁護士など、信託に詳しい専門家の支援が必要です。
- 初期費用がかかる → 信託財産の登記手続きや、契約書の作成などでコストが発生します。
- ご家族・ご親族の理解が追いつかないことも → ご家族・ご親族が、全体で制度を共有しておくことが大切です。
以上のように、制度利用の際には、メリットや注意点を押さえ、ご家族・ご親族間で共有しつつ、検討しましょう。
家族信託が役立つのはこんなケース!活用事例を紹介

家族信託は、「こういう状況だからこそ活用したい」という明確なケースで効果を発揮します。ここでは、現場でも実際によく相談される活用例を3つご紹介します。
ケース① 自宅不動産を将来どうするか迷っている場合
ご本人が、自宅でひとり暮らしをしており、将来は施設入所や売却も視野に入れている。そんなときに家族信託を活用すれば、ご本人の判断力が落ちても、ご家族が不動産の売却や管理をスムーズに進められます。

成年後見制度では制約が多く、裁判所の許可が必要になるケースがあるため、家族信託の柔軟性が活きる代表例です。
ケース② 認知症のご家族の資産を管理したいとき
たとえば、ご本人名義の通帳から毎月の生活費や介護費を出しているが「いずれ手続きが難しくなりそう」という不安がある場合です。
このようなとき、家族信託によって、ご家族が事前に「信託口座」でお金を管理できるようにしておくと、混乱を防げます。
特に、兄弟間で資産管理に協力が得にくい場合でも「契約で決まっている」ことで、トラブル防止になります。
ケース③ 相続よりも「今の生活管理」を重視したいとき
遺言や相続の前に、まずは「今の暮らしが回ることが大事」という方には、家族信託が最適です。
「毎月の生活費の出金」や「定期的な支払い」「不動産の維持管理」などを、今からスムーズに引き継げるのが、家族信託の強みです。
家族信託の手続きと費用は?専門家に依頼する場合の流れ

「家族信託が良さそうだけど、手続きが難しそう…」そう感じる方も多いかもしれません。
たしかに家族信託は専門的な制度ですが、信託に詳しい司法書士や弁護士に相談すれば、スムーズに進められます。
一般的な手続きの流れ(相談〜契約書作成〜信託開始)
手続きの流れは、以下のとおりです。
- 家族内での話し合い・合意 → まずは親子で「何のために信託をするか」を明確にしておくことが大切です。
- 専門家への相談(司法書士・弁護士など)→ 家族構成や財産状況に合わせて、信託契約の設計をサポートしてくれます。
- 信託契約書の作成・締結 → 法的な文書として、委託者(親)と受託者(子)で契約を結びます。
- 信託口口座の開設・不動産の名義変更(必要に応じて)→ 金融機関や法務局での手続きが必要になることもあります。
かかる費用の目安と内訳(司法書士・信託登記など)
家族信託にかかる費用は、ケースによって異なります。以下は、あくまでも目安です。制度を検討する際の参考にしてください。
トータルで30〜50万円前後になることもありますが、「専門家の関与」「信託財産の額」「不動産の有無」などによって変動します。
どこに相談すればいい?相談先の選び方
家族信託は、比較的新しい制度です。よって、信託に詳しい専門家を選ぶことがとても重要です。

インターネットで「家族信託 司法書士 〇〇市」などで検索すれば、無料相談を受け付けている事務所も見つかります。
また、家族信託の実績のある事務所に相談したい場合には、家族信託の契約数NO.1の「おやとこ」に相談する方法もあります。
司法書士などの家族信託の専門家が、お客様のご状況に合わせた家族信託の無料相談を行っています。全国に7拠点を構え、年間数千件もの家族信託の問い合わせに対応しています。
まとめ:家族信託と成年後見制度、どう選ぶ?

柔軟に備えたいなら「家族信託」が適しています。また、法的に守りたいなら「成年後見制度」が向いているかもしれません。
大切なのは「どちらが、ご自身に合っているか?」を考えることです。
そんなご家庭には、自由度の高い家族信託が向いています。信託契約に詳しい専門家に相談すれば、状況に合わせた柔軟な設計が可能です。

「まだ先の話」と思っていても、介護はある日突然必要になります。私は、ケアマネジャーとして、そういったケースを多く見てきました。
あらかじめ、困りごとを予防しておくことが大切です。
「とりあえず、どんな仕組みか詳しく聞きたい」と考えている方は、家族信託の契約数NO.1の「おやとこ」の無料相談をご活用ください。
司法書士などの家族信託の専門家が、お客様のご状況に合わせた家族信託の無料相談を行っています。全国に7拠点を構え、年間数千件もの家族信託の問い合わせに対応しています。