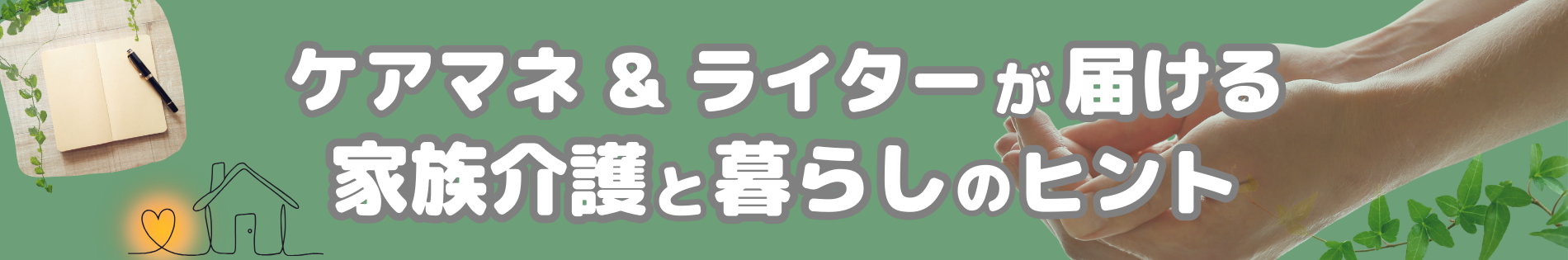「親を施設に入れたいけれど、お金がなくてどうすればいいのか分からない…」
そんな悩みを、ひとりで抱えていませんか?

介護にかかる費用は、多くの家庭にとって大きな負担です。しかし、経済的な事情だけで、必要な施設入居を諦める必要はありません。
- 「介護のお金がない」ときの対処法
- 相談先や費用を抑えられる施設の種類
- 知っておきたい公的な負担軽減制度
現役ケアマネジャーが、施設入居の費用を抑える方法について解説いたします。
この記事を読めば「この方法ならやっていけそうだ」と思える道筋が見えてくるはずです。ぜひ最後までお読みください。
ひとりで悩まないで!頼れる2つの無料相談窓口

介護と費用の問題は、非常に複雑です。まずは、専門家の力を借りることを検討しましょう。ここでは、無料で利用できる相談窓口を2つ紹介します。
地域の総合相談窓口「地域包括支援センター」
「地域包括支援センター」は、市区町村が設置している高齢者のための公的な総合相談窓口です。介護に関することはもちろん、医療や福祉、金銭的な問題まで、高齢者に関するあらゆる悩みを無料で相談できます。
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーといったさまざまな分野の専門家が在籍しています。そのため、多角的な視点から、今の状況に最適なアドバイスや情報を提供してもらえるのが大きな強みです。

「何から手をつけていいか全く分からない」という方は、まずは地域包括支援センターに電話してみることをお勧めします。
担当のケアマネジャー
ご本人が要介護認定を受け、介護保険サービスを利用している場合、最も身近で頼れる存在が担当のケアマネジャー(介護支援専門員)です。ケアマネジャーは、日頃からご本人の心身の状態やご家庭の状況を把握しており、その情報を踏まえて具体的な提案をしてくれます。
例えば、費用を抑えられる施設の紹介や、負担を軽減する公的制度の案内、申請手続きのサポートまで幅広く対応が可能です。介護に関する不安や疑問も含めて、まずは気軽に相談してみましょう。
親を施設に入れるお金がない…今すぐできる7つの対処法

専門家への相談と並行して、具体的にどのような選択肢があるのかを知っておくことが重要です。今日からできる、具体的な対処法を7つご紹介します。
① 費用を抑えられる公的な施設を探す
介護施設には、民間が運営する有料老人ホームのほかに、国や自治体からの補助金で運営されている「公的施設」があります。公的施設は、入居一時金が不要な場合が多く、月々の利用料も所得に応じて軽減されるため、費用を抑えることが可能です。
代表的なものに、特養・老健・ケアハウスなどがあります。経済的な負担を軽くするためには、まずこれらの公的施設への入居を検討するのが基本です。
② 費用担を軽くする制度を利用する
日本の介護保険制度には、所得が低い方の負担を軽減するための様々な仕組みが用意されています。これらの制度を知っているかどうかで、毎月の支払額が数万円単位で変わることも少なくありません。
例えば、施設の食費や部屋代の負担に上限を設ける「特定入所者介護サービス費」や、月々の自己負担額が一定額を超えた場合に超過分が払い戻される「高額介護サービス費」などがあります。利用できる制度がないかを確認しましょう。
※費用を抑える制度や相談先については、こちらの記事で詳しく解説しています。
③ 親の資産状況を正確に把握する
具体的な資金計画を立てるためには、ご本人の資産状況を正確に把握することが不可欠です。どのくらいの年金収入があり、どのくらいの預貯金があるのかが分からないと、対策の立てようがありません。
年金、預貯金、不動産、有価証券などをリストアップし、現状を正確に把握することが大切です。

お金の話は、親子でも切り出しにくいものです。「今後の介護プランを一緒に考えるために」という目的を伝え、理解を得ることから始めましょう。
④ 不動産を活用して資金を作る
ご本人が持ち家などの不動産を所有している場合、それを活用して介護資金を作る方法もあります。
代表的なのは、自宅を担保にお金を借りる「リバースモーゲージ」という制度です。また、一般社団法人などが自宅を借り上げ、安定した家賃収入を保証してくれる「マイホーム借り上げ制度」といった選択肢もあります。
ただし、それぞれメリットデメリットがあるので、ご家庭に合っている制度かどうかを確認しておきましょう。
⑤ 世帯分離で自己負担額を減らす
親と子の世帯を、住民票の上で別々にする「世帯分離」という手続きを行うことで、介護費用の自己負担額が下がる場合があります。
介護保険サービスの自己負担割合や各種負担軽減制度は、世帯の所得によって判定されます。そのため、世帯分離によって「住民税非課税世帯」になると、負担が軽くなる可能性があるのです。
ただし、ご家族の国民健康保険料が上がるといったデメリットもあるため、必ず役所の窓口でシミュレーションをしてもらいましょう。
⑥ 最終手段として生活保護を申請する
ここまで紹介した様々な方法を試しても、どうしても費用が足りないという場合には、最終的な手段として生活保護の申請を検討します。お住まいの地域の福祉事務所が相談窓口です。

生活保護を受給すれば施設費用が賄える場合もあります。ただし、受け入れ可否は施設によって異なるため、事前確認が必要です。
⑦ 施設探しのプロに相談して最適な施設を見つける
全国には数多くの介護施設があり、その料金体系やサービスはさまざまです。予算内でご本人の希望に合う施設を自力で探し出すのは、大変な時間と労力がかかります。
そこでおすすめなのが老人ホーム紹介サイトの活用です。専門の入居相談員に予算や希望条件を伝えるだけで、数多くの施設の中から最適な候補を無料で提案してくれます。
お金の悩みも含めて親身に相談に乗ってくれるので、効率的に施設探しを進められます。
そもそも介護施設の費用はいくら?誰が払うべき?

まずは介護施設の費用に関する基本的な知識と、誰が支払うべきかというルールについて確認しておきましょう。
【一覧表】施設の種類別・費用の目安
介護施設の費用は、公的施設か民間施設か、また提供されるサービス内容によって大きく異なります。まずは、代表的な施設の種類と費用の目安を一覧で見て、全体像を掴みましょう。
| 施設の種類 | 運営主体 | 初期費用(入居一時金) | 月額費用目安 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 公的 | 0円 | 5〜15万円 |
| 介護老人保健施設(老健) | 公的 | 0円 | 8〜20万円 |
| 有料老人ホーム | 民間 | 0〜数千万円 | 15〜40万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 民間 | 15〜30万円(敷金) | 10〜25万円 |
※上記の金額は、あくまでも参考値です。公的施設は費用が安い一方、待機者が多く入所までに数ヵ月〜数年かかることもあります。また、有料老人ホームなどの民間施設は選択肢が広い分、費用も高額になる傾向があります。
費用の内訳:何にいくらかかるのか
施設の費用は、大きく分けて入居時に支払う「初期費用(入居一時金)」と、毎月支払う「月額費用」の2つがあります。
初期費用は、有料老人ホームなどで必要となる場合が多く、いわば「家賃の前払い金」のようなものです。施設によって0〜数千万円までと大きな幅があります。
一方、主な月額費用は、以下のとおりです。
- 居住費(家賃)
- 食費
- 管理費
- 介護サービス費の自己負担分(1〜3割)
- その他雑費(おむつ代、理美容代など)」
気になる点は、事前に施設へお問い合わせください。
親の介護費用、支払う義務は誰にある?兄弟姉妹で揉めないために
施設の費用は、原則としてご本人の年金や資産から支払います。それでも足りない分を、子どもが支援するのが一般的です。
法律(民法第877条第1項)では、親子や兄弟姉妹は互いに扶養する義務があると定められています。具体的には、親子には強い扶養義務がありますが、兄弟姉妹の場合は「特別な事情があるときに限る」とされています。
誰がいくら負担すべきかという具体的な割合についての決まりはありません。そのため、兄弟姉妹がいる場合は、事前に全員でしっかりと話し合うことが非常に重要です。
後々のトラブルにならないように、しっかり話せる場を持ちましょう。

ご家族によっては、金銭的な負担が難しい場合もあります。そんなときは、通院の付き添いをしてもらうなど、何かしらの役割を担ってもらうのも一つの方法です。
【参考】法令検索「民法第877条第1項」
【詳細解説】費用を抑えて入居できる施設

ここでは、経済的な負担を抑えたい場合に主な選択肢となる4種類の施設について、詳しく解説します。
特別養護老人ホーム(特養):費用が安く、終身利用も可能
特別養護老人ホーム(特養)は、社会福祉法人などが運営する公的な施設です。最大の魅力は、入居一時金が不要で、月額費用も5万円〜15万円程度と非常に安いことです。所得に応じた負担軽減制度もあり、終身にわたって安心して生活できます。
ただし、入居するには原則として要介護3以上の認定が必要です。費用が安いことから非常に人気が高く、地域によっては入居までに数ヶ月から数年単位で待機する必要があるのが難点です。
介護老人保健施設(老健):在宅復帰を目指すリハビリ施設
介護老人保健施設(老健)は、病院を退院した後、すぐに自宅での生活に戻るのが不安な方が、リハビリテーションを行うための施設です。医師や理学療法士などが常駐しており、医療ケアが手厚いのが特徴です。
入居一時金は不要で、月額費用は8〜20万円程度が目安です。ただし、老健はあくまで在宅復帰を目指すための中間施設という位置づけであり、入居期間は原則3〜6ヶ月と限られています。終身利用はできない点に注意が必要です。
軽費老人ホーム(ケアハウス):自立した生活が基本の方向け
軽費老人ホームは、身の回りのことは自分でできるものの、自立した生活に不安がある高齢者向けの施設です。その中でも「ケアハウス」と呼ばれるタイプが主流で、食事や見守り、緊急時対応などのサービスが受けられます。
入居一時金は0〜30万円程度、月額費用は6〜20万円程度と、比較的安価に設定されています。所得に応じた料金体系になっているため、低所得の方でも入居しやすいのが特徴です。
入居一時金0円の有料老人ホーム:初期費用を抑えたい方向け
有料老人ホームは民間施設のため費用が高いイメージがあります。しかし、中には、初期費用がかからない「入居一時金0円プラン」を用意している施設もあります。
これにより、手元に大きな資金がない場合でも入居のハードルが大きく下がります。月額費用は、施設によってさまざまです。長期的な視点で、月々の支払いを継続していけるかどうか、慎重な資金計画が求められます。
【詳細解説】必ず知っておきたい!介護費用の負担を減らす公的制度

公的な負担軽減制度をうまく活用することで、家計への負担を減らせるケースがあります。ここでは、必ず押さえておきたい5つの制度を詳しく解説します。
特定入所者介護サービス費:食費・居住費の負担を軽減
「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」は、所得や預貯金が一定以下の人を対象に、介護保険施設(特養や老健など)の食費と居住費の自己負担額に上限を設ける制度です。

施設費用の食費と居住費が軽減されるため、非常に効果の大きい制度です。この制度を利用するには、お住まいの市町村に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
【参考】西東京市「特定入所者介護サービス費」
高額介護サービス費:月の自己負担額に上限を設定
「高額介護サービス費」は、1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額(1〜3割の部分)の合計が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。
これにより、要介護度が高く、たくさんの介護サービスを利用した場合でも、月々の負担が際限なく増えるのを防げます。多くの場合、対象者には自治体から申請書が送られてきますが、初回は自分での申請が必要な場合もあるため確認が必要です。
【参考】厚生労働省「高額介護サービス費制度が見直されます」
高額医療・高額介護合算療養費制度:医療費と介護費の合計額を軽減
「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額をすべて合算し、それでもなお基準額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。
医療費と介護費の両方の負担が重くなりがちな世帯にとっては、大きく費用を抑えられます。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外となる点や、世帯分離をしていると利用できなくなる可能性がある点には注意が必要です。
【参考】厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
低所得で生計が困難な方を対象に、社会福祉法人が運営する施設やサービスを利用した際の負担を軽減する制度です。
この制度を実施している法人のサービスを利用した場合に限られますが、施設サービス費や食費、居住費などの自己負担額が軽減されます。対象となるかどうかは、市町村の窓口や利用を検討している施設に確認してみましょう。
【参考】横浜市「社会福祉法人による利用者負担軽減について」
医療費控除・障害者控除
確定申告を行う際に、これらの控除を利用することで、所得税や住民税の負担を軽くできます。
「医療費控除」では、支払った医療費だけでなく、特養の施設サービス費や、老健の費用なども対象になります。また、医師の証明書があれば、おむつ代も控除の対象です。
「障害者控除」は、障害者手帳を持っていなくても、市町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ、控除の対象となる場合があります。
【参考】国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
まとめ:お金がなくても親を施設に入れる方法は必ず見つかる

今回は「親を施設に入れたいけれどお金がない」という悩みに対する具体的な解決策を解説しました。
最後に、この記事のポイントを振り返りましょう。
- ひとりで抱え込まない:まずは「地域包括支援センター」や「ケアマネジャー」など無料の専門窓口に相談しましょう。
- 公的制度をフル活用:費用を抑えられる公的施設(特養など)や、食費・居住費を軽減する制度などを最大限に活用することが重要です。
- 家族で話し合う:介護費用は親の資産で賄うのが基本ですが、不足分は兄弟姉妹で協力し、役割分担を明確にすることがトラブルを防ぎます。
- 多様な選択肢を知る:公的施設だけでなく、入居金0円の民間施設や、不動産活用、世帯分離など、打てる手は数多くあります。

お金の問題は、とても大きな問題です。しかし、正しい情報を知り、適切な手順を踏めば、解決の糸口は必ず見つかります。大切なのは、諦めずに一つずつ行動を起こしていくことです。
この記事を参考に、施設入居に関する費用について理解を深めていただければ幸いです。