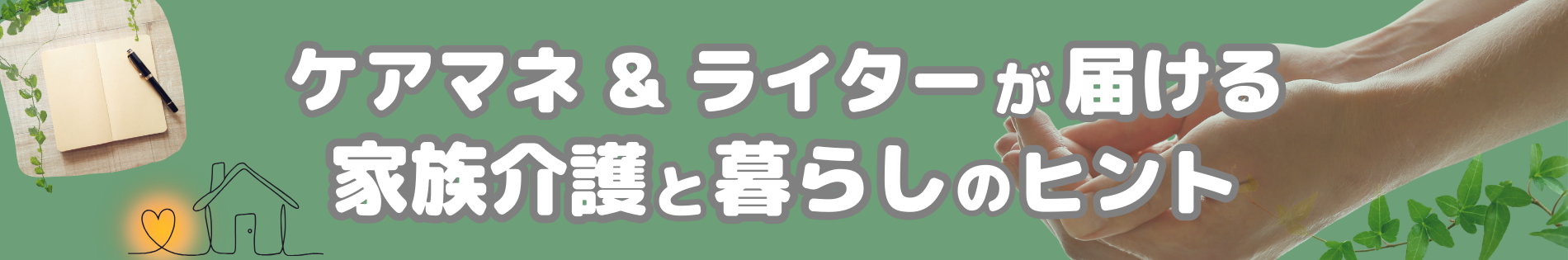「ショートステイを利用したら、認知症が進んだ気がする」「本人が嫌がるので、無理に利用させるのは気が引ける」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
症状が悪化したように見えるのには、はっきりとした理由があります。その原因と対処法を知ることで、ショートステイを安心して利用することも可能です。

ショートステイは、在宅介護に欠かせません。活用できるように、正しい知識を!
この記事では、現役ケアマネジャーが「ショートステイで認知症が進む」という不安の原因と、具体的な対策を解説します。ぜひ最後までお読みください。
「ショートステイで認知症が進む」は誤解?「せん妄」との違い

「ショートステイを利用したら認知症が進んでしまった」というご相談は、ケアマネジャーとして働く中でよく耳にします。
しかし、多くの場合、認知症の進行ではなく、環境の変化による一時的な混乱、特に「せん妄」という状態が原因です。
- 環境変化が引き起こす一時的な混乱
- 認知症の悪化ではなく「せん妄」の可能性
- 認知症とせん妄の見分け方
この違いを理解することで、ご家族の不安を解消し、適切に対応できます。それでは、順番にみていきましょう。
「認知症が進んだ」と感じる本当の理由:環境変化による一時的な混乱
ショートステイからの帰宅後に混乱した様子が見られる主な原因は「環境の変化」です。認知症の方は、記憶力や判断力の低下により、新しい環境に適応することが苦手です。
住み慣れたご自宅と異なる部屋、見慣れないスタッフや他の利用者など、多くの変化が一度に起こることで、大きなストレスや不安を感じてしまいます。その結果、認知症の症状が一時的に強くなったように見えるのです。
その症状、認知症の悪化ではなく「せん妄」かも
急な症状の変化は、認知症の進行ではなく「せん妄」という一時的な意識障害の可能性があります。
せん妄とは、身体的な不調や薬の影響、そして環境の変化といったストレスが引き金となって、急に混乱状態に陥ることを指します。

せん妄が原因なら、数日から数週間で、症状は落ち着きます。ちなみに、せん妄は、健康な人でも起こることがあります。
まずは、落ち着いて症状を観察することが重要です。
【ケアマネ解説】認知症とせん妄、ここが違う!見分け方のポイント
認知症とせん妄の最も大きな違いは、症状の「発症スピード」と「変動」です。認知症は数ヶ月から数年かけてゆっくりと進行する点が特徴です。
一方、せん妄は「きっかけ」がはっきりしており、数時間から数日のうちに急激に発症します。また、一日の中でも症状が大きく変動するのも特徴です。重要な点として、せん妄は、原因が取り除かれれば、数日から数週間で改善します。
「認知症とせん妄の違い」を知ることが、適切に対応するためのポイントなのです。
【参考】川崎医科大学附属病院「せん妄って何だろう」
認知症の進行を防ぐ!ショートステイを成功させる3つの準備術

ショートステイで穏やかに過ごしてもらうためには、事前準備が重要です。ポイントは、以下の3つです。
- ご本人の「人となり」を伝える
- 愛用の品を持参し、安心できる環境を整える
- 短期間の利用から始め、徐々に慣れてもらう
それでは、順番にみていきましょう。
ポイント①「情報共有」:ご本人の”人となり”を施設に伝える
ショートステイでの混乱を避けるには「ご本人の情報を、詳しく施設へ伝えておくこと」が大切です。施設スタッフは、初めて会う方の性格やこれまでの生活歴までは分かりません。
ご家族だからこそ知っている「その人らしさが伝わる情報」を事前に共有することが、個別ケアの第一歩となります。

不安になったとき、どうすれば落ち着くかなど、ご自宅での様子をスタッフに話しておくと安心ですね。
ポイント②「環境整備」:「ここは安全な場所」と感じてもらう工夫
認知症の方は、見慣れない場所では大きな不安を抱えるものです。不安を和らげるためには、ご自宅に近い環境を整え「ここは安全な場所だ」と感じてもらえるように工夫しましょう。
具体的には、以下のようなものを持参するなどの工夫が有効です。
- 使い慣れた湯呑み
- いつも使用しているクッション
- ご家族の写真
また、可能であれば、ベッド周りの配置を自宅の寝室に似せてもらうよう施設にお願いするのも良いでしょう。
こうした小さな工夫が、ご本人の心の安定につながり、穏やかに過ごせるきっかけとなります。
ポイント③「利用計画」:短期間から始める「慣らしショートステイ」
ショートステイを始める際は、いきなり長期間利用するのではなく、短い日数から試す「慣らしショートステイ」をおすすめします。
認知症の方は、環境の変化への順応が苦手です。慣れない長期利用は、混乱を招く原因になりかねません。

まずは、1〜2泊といった短期間からスタートし、ご本人の様子を見ながら、少しずつ日数を延ばしていくのが理想的です。
ご本人の負担を最小限に抑え、ショートステイという環境を受け入れやすくしましょう。
ご本人がショートステイを嫌がる…不安を和らげる3つの対応術

ご本人がショートステイを嫌がるのには、必ず理由があります。大切なのは、その心理を理解し、適切に対応することです。
- 「行きたくない」という言葉の裏にある心理を読み解く
- 拒否された際は、まず気持ちを受け止める
- ご家族だけで抱え込まず、第三者の力を借りる
以上の対応で、ご本人の不安を和らげ、スムーズな利用につなげられます。
「行きたくない」の裏にある心理と具体的な声かけのヒント
ご本人が「行きたくない」と言うのは、言葉の裏に見慣れない場所への不安や、自分のペースを乱されたくないという心理が隠れているからです。
認知症の方は環境の変化に弱く、行き先が理解できないため強い不安感を感じることがあります。
声かけの際は、ただ「ショートステイに行くよ」と伝えるのではなく「お風呂に入りに行こう」「お友達に会いに行こう」など、ご本人が前向きになれるような目的を伝えてみましょう。
拒否や帰宅願望が強い時の対応:まずは気持ちを受け止めること
拒否的な態度や言動が強い場合、最も重要なのは、ご本人の気持ちを否定せずに受け止めることです。「行きたくないんだね」「何か心配なことがあるの?」と、まずは共感的な姿勢で話を聞くことが求められます。
無理強いをしたり、頭ごなしに否定したりすると、かえって不安や抵抗感を強めてしまいます。ご本人の言葉にゆっくりと耳を傾け、不安な気持ちを吐き出してもらうだけで、落ち着きを取り戻すことも少なくありません。
まずは冷静に、ご本人の気持ちに寄り添うことを心がけましょう。
どうしても難しい時はケアマネジャーなど第三者の力を借りる
ご家族だけでは難しい場合、ケアマネジャーや施設の職員といった第三者の力を借りるのが有効です。
ご家族には感情的になってしまう方でも、第三者から冷静に説明されると、素直に聞き入れられるケースは少なくありません。

ケアマネジャーからお話すると、意外と聞き入れてくださることもあるんです。ひとりで抱え込まず、専門家を頼ることも、大切な介護の技術の一つです。
認知症が「進む」のを防ぎ家族も休む|ショートステイの賢い活用法

ショートステイは、ご本人にとっても、ご家族にとっても重要な役割があります。
- 介護者の心身の休息(レスパイトケア)
- ご本人への刺激と社会との繋がり
以上のメリットを理解し、在宅介護を続けていくためにショートステイを活用しましょう。
介護者のための「レスパイトケア」:心と体を休める大切さ
ショートステイには、ご家族のための「レスパイトケア(休息)」という大切な目的があります。日々の介護による心身の疲れやストレスは、ご家族にとって大きいものです。
介護者が休息を取ることで、気持ちに余裕が生まれ、再び穏やかな気持ちでご本人と向き合えます。介護から一時的に離れる時間を持つことは、決して手抜きではなく、介護を続けていくために不可欠なことです。
本人にとってのメリット:刺激と社会との繋がり
ショートステイは、ご本人にとって良い刺激となり、社会との繋がりを保つ機会になります。ご自宅での生活は安心できる反面、単調になりがちです。
ショートステイを利用すると、施設の職員や他の利用者といった家族以外の人と交流する機会が生まれます。レクリエーションへの参加や、普段と違う環境で過ごすことが、脳への良い刺激となり、心身機能の維持に繋がることも期待できます。
ご本人にとって、ショートステイが生活にメリハリをもたらす、前向きなイベントとなる可能性もあるのです。
知っておきたいショートステイの流れと「断られた」時の対処法

ショートステイを利用するためには、手続きの流れと、万が一利用を断られた場合の対処法を知っておくことが大切です。正しい知識を持つことで、いざという時に慌てず、ご本人に合ったサービスにつなげられます。
- 利用開始までの簡単な4ステップ
- 利用を断られる主な理由と確認事項
- 断られた場合の選択肢「医療型ショートステイ」
これらのポイントを押さえ、計画的にショートステイの利用を検討しましょう。
相談から利用開始までの簡単4ステップ
ショートステイの利用は、基本的に以下の4つのステップで進みます。
- ステップ1:まず、サービスの利用に必要となる「要介護認定」を受けます。
- ステップ2:次に、担当のケアマネジャーに相談し、ショートステイを組み込んだ「ケアプラン」を作成してもらいます。
- ステップ3:ケアマネジャーと連携しながら、ご本人に合った施設を探し、見学に行きます。
- ステップ4:利用したい施設が決まったら、契約手続きを進めます。

利用に関する手続きは、ケアマネジャーが中心となってサポートします。利用したいときは、まずはケアマネジャーへ相談しましょう。
※介護保険申請について、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
ショートステイを断られる主な理由と確認すべきこと
ショートステイの利用を断られる場合、必ず理由があります。例えば、以下のような理由です。
- 経管栄養、喀痰吸引などの医療的ケアが必要
- 他の利用者への暴力・暴言が見られる
- 帰宅願望が非常に強く落ち着けない
などの症状があり、施設が対応できないケースです。
利用を断られた際は、具体的な理由を施設にしっかりと確認しましょう。理由が分かれば、対策を立てやすくなります。
もし断られても大丈夫!「医療型ショートステイ」という選択肢
一般的なショートステイが難しくても、あきらめる必要はありません。特に、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが理由で断られた場合、「医療型ショートステイ」という選択肢があります。
これは「短期入所療養介護」とも呼ばれ、介護老人保健施設や病院などが提供するサービスです。医師や看護師が常駐しているため、医療体制が整っており、安心して利用できます。
ご本人の状態に合わせて、こうした選択肢があることを知っておくことが重要です。
まとめ|ショートステイは認知症の方とご家族を支える「チームケア」

「ショートステイで認知症が進む」という不安は、正しい知識を持ち、事前に準備することで解消できます。ショートステイを上手に活用するために、この記事のポイントを簡潔にまとめました。
- 「認知症が進む」は「せん妄」かも:利用後の混乱は、多くの場合、環境の変化による一時的な「せん妄」です。認知症の進行とは異なるため、まずは冷静に症状を見極めましょう。
- ポイントは「事前準備」:ご本人の情報共有、愛用品の持参、短期間からの利用計画など、ご家族ができる準備がご本人の安心に繋がります。
- 「嫌がる気持ち」に寄り添う:拒否には、必ず理由があります。気持ちを受け止め、ケアマネジャーなど第三者の力も借りましょう。
- 家族のための休息でもある:ショートステイは、介護を担うご家族が心身を休めるための大切な時間(レスパイトケア)でもあります。
- 断られても次の選択肢がある:もし利用を断られても、理由を確認し「医療型ショートステイ」など他の選択肢を検討することが可能です。
ショートステイは、ご本人とご家族の生活を支える「チームケア」のひとつです。

介護は、ひとりで抱え込むものではありません。私たちケアマネジャーをはじめ、さまざまな専門職が皆様を支えますので、いつでもお気軽にご相談ください。